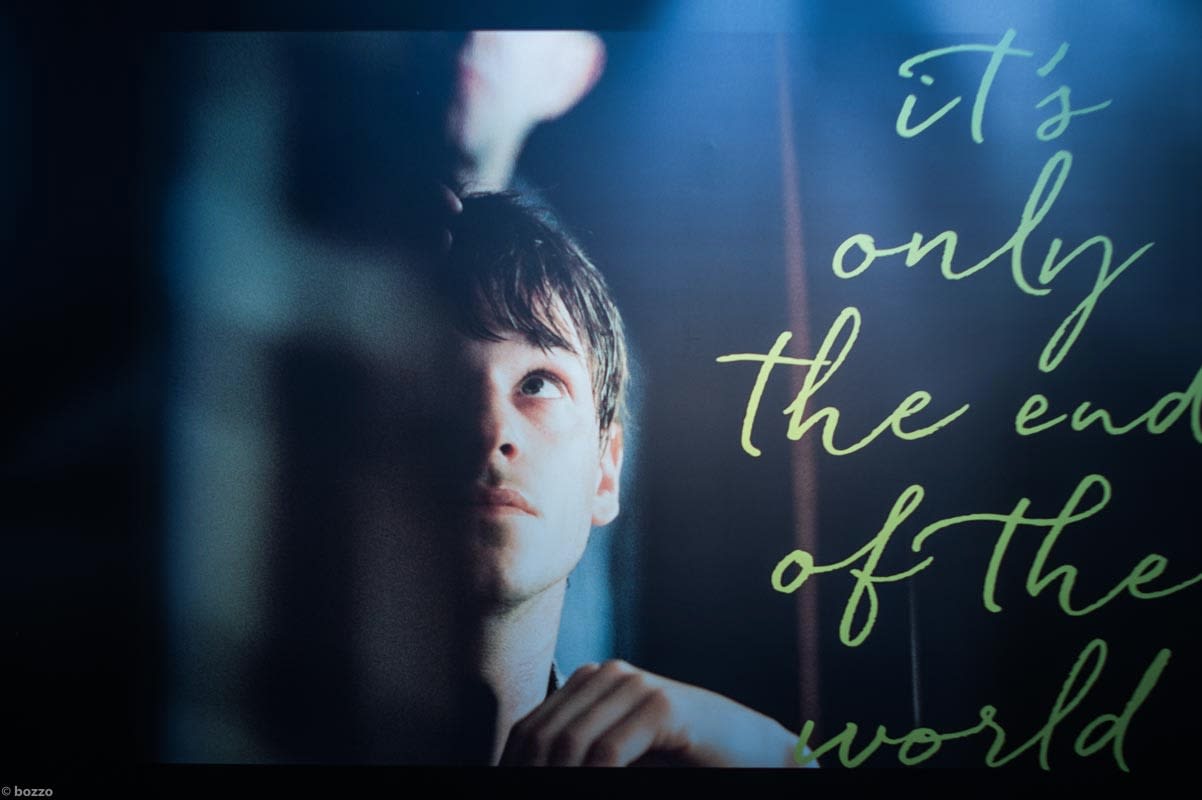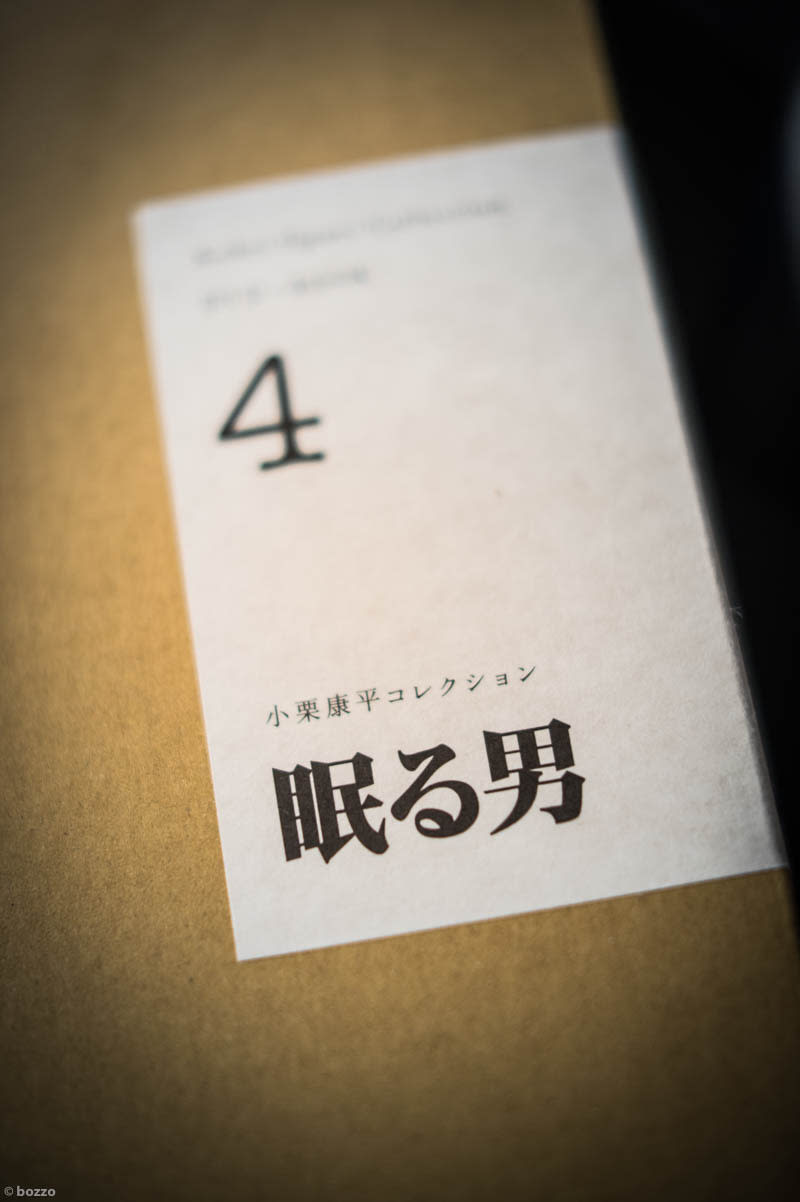三上智恵監督最新作
『標的の島_風かたか』を観る!
映画の日にポレポレで観てきました、三上作品。
冒頭の古謝さんの唄声でもう、怒りと涙の感情が大きく揺さぶられ、
2時間ずうっと揺さぶられっぱなしでした。
怒、怒、怒、怒、です。
沖縄を離れて8年。ずうっとずうっと怒りっぱなしですが、
平田守さんの肉薄した映像に魅入って、
高江や辺野古で座り込みしてるような心持ちで、
機動隊に対峙している自分がいました。
「エアシーバトル構想」…初めて耳にするコトバですが、
云ってることはよぉ〜くわかります。
日米地位協定によって、戦後72年間ずっとこの国は、アメリカの下に居るのですから。
領空権もなく、自衛隊の最高指揮官はアメリカという、
植民地事態なまま今まで来たんですから。
自衛隊の存在意義ってなんだと思います?
あれは米指揮の許に在る軍隊ですから、憲法九条には抵触しない…と。
そういう理屈で成立した組織なの、ご存知でしたか?
50年に警察予備隊として結成されたときの名目は、
国連安保理決議第84号により
国連軍がアメリカに委ねた統一指揮権のもと利用される…
という狡猾なカタチで今まで存続してきた軍隊なのです。
(矢部宏治著「日本はなぜ戦争ができる国になったのか」より)
奄美大島から与那国島までの島嶼をそのまま主戦場にして
中国アメリカの直接対決を避け、
米従軍である自衛隊がその最前線で抵抗する…というのが、
「エアシーバトル構想」です。
今着々と進んでいる与那国、石垣、宮古、
そして辺野古の自衛隊基地整備は、
まさしく中国の標的となるべく進められているものなのです。
辺野古は普天間基地の代替施設という決まり文句は、
真実をねじ曲げた小賢しいレトリックでしかなく、
その真意は米「エアシーバトル構想」に従軍する
自衛隊のベース基地となるものです。
すべてが【国連軍】という偽善の下に
ぶら下げられた回りくどい修飾文の、
別役実の不条理劇そのままの状況。
そしてそして、これまた厄介なことに、
基地反対で座り込みを続ける山城さんたちを
蹴散らす機動隊の面々は、
米国→隷属日本政府→防衛省→警察という指令系統の傘の下で、
オノレの感情を殺し、思考を停止したロボットのような様相で、受動態として壁を作っている。
水俣病からフクシマへと連綿続くこの責任者不在の原理。
死者の声を聞いて死者と共に座り込みをし、
未来の子どもたちを悲しませたくない…という一心で、
80歳を越えて尚カラダを張っているおじぃおばぁたちに、
対峙する機動隊の若者たちは、任務遂行のためでしかない…という不均衡な構図。
生身の人間の苦しみに対して真っ向から受け止めず、
組織や制度を楯に巧妙にズラシを施し、
搦め捕ろうとする「欺しのテクニック」。
その最たる法律が【共謀罪】です。
この国はホントに、ホントに、どこまで恥さらしなのか。
どこまで米国の敗者として魂を売り飛ばし続けるのか。
三上さんが映画監督になってまで全国行脚しなければ、
この不条理劇の狡猾さが伝わらない…
そのことが何よりも哀しいことだし、
ひとりでも多くの人が、
この詐欺師ニッポンの国家の成り立ちに、
この映画を通して気づいて貰えれば…と、
ただただ願うだけなのです。
怒、怒、怒、怒…。