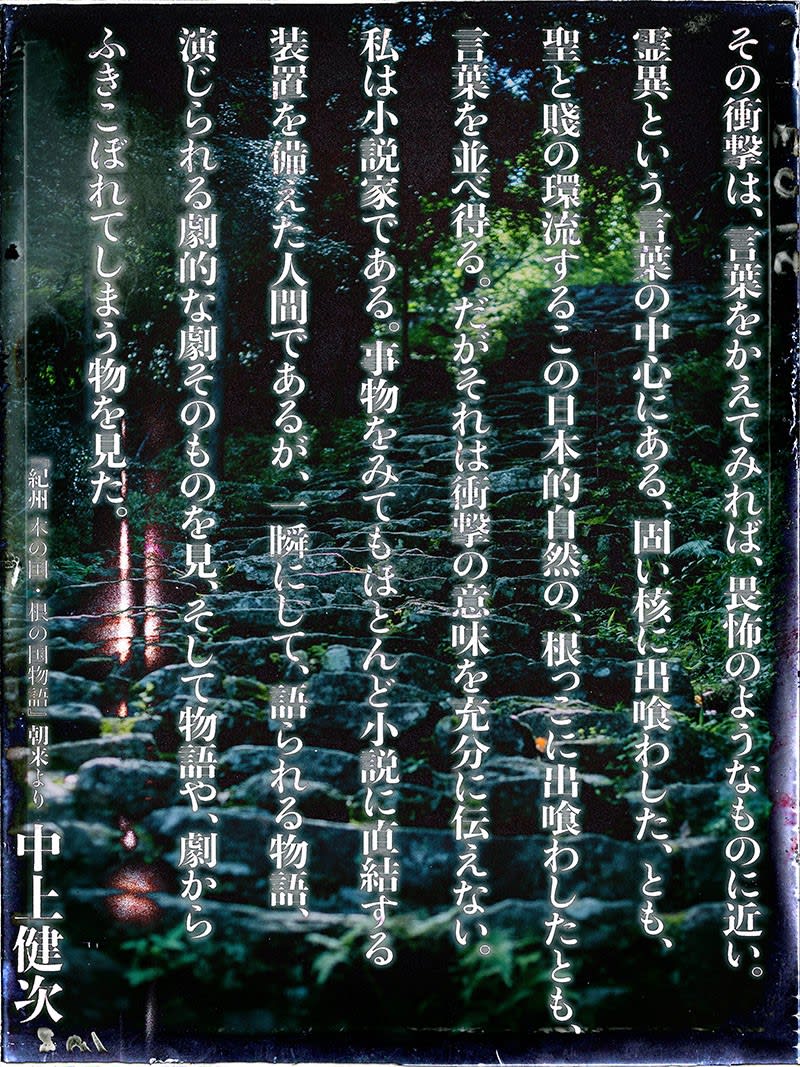【宝島】自分の中の他者を知る。
『もう風も吹かない』観劇で、炙り出された構図は、自己の未済性…常に本来の自分に成り切ろうとして、果たせないでいる状態。それって、『宝島』におけるオキナワそのもので、ハッとした。オキナワにおいては、その未済性が完結してしまった不条理な状態で、未来が描けない鬱状態に陥っている。『もう風~』における2040年の日本も「出口なし」な鬱状態ゆえに、キノコ隊員は飲酒による逃避で、現状から逃れようとしたのだ。『宝島』における希望と『もう風~』のそれは、『宝島』においては「ダブル」という、自分の中に他者を介入させた「実体」で呈示された。オキナワを陥れたアメリカを内在することで、混淆→ミックスが糸口となり、未来への微かな希望が射し込まれる。『もう風~』では、派遣国へ赴くことで得られる体験が、他者を内在し未来を導くという「行動」で締め括られていた。いずれにしても、未来が描けない「未済性の完結」打破には、「他者性」の獲得が必須なのである。いま現在跋扈する排他的動向は「他者」の獲得を拒絶した状態であり、いわば「純粋培養」へ舵を切った状態である。生態系としては、「雑種強勢」は良好な環境下より不良環境下で大きく発現するようである。これを真理と願いたい。「人間」は“人のあいだ”と記すのだから。
#photobybozzo